|
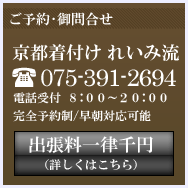
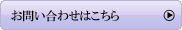
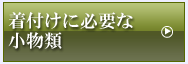

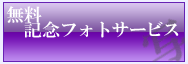 
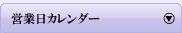
|
 |
|
| こちらのページでは着物・着付けに関する基本的な事柄を、初心者の方にも分かりやすい言葉でまとめてみました。参考にご覧下さい。 |
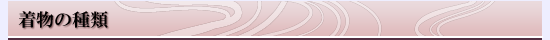 |
|
|
振袖
未婚女性の第一礼装。袖丈(75センチから105センチ程度)の長い着物のことで、婚礼のお色直しや結婚披露宴、パーティー等晴れやかなシーンで用います。現在では、成人式や卒業式といった式典で最も多く着用されています。

黒留袖
既婚女性の第一礼装。江戸褄模様五つ紋付きが特徴です。

色留袖
黒留袖の五つ紋に対して、三つ紋や一つ紋として着る事もあります。結婚式や披露宴の席で着用されています。

訪問着
未婚女性、既婚女性のお着物。黒留袖の五つ紋に対して、三つ紋や一つ紋として着る事もあり結婚式や披露宴の席で着用されます。

付け下げ
左右の身頃や肩から袖にかけて模様がつながらないのが特徴です。訪問着を簡略化した気軽で小紋より格の高い着物です。披露宴のお呼ばれ、パーティ等訪問着として変りなく着ていただけます。

色無地
白生地を単色に染めた着物の事。控えめで上品な装いとして結婚式や結納、お茶会、入卒式、七、五、三。お宮参り、観劇、食事会等様々な面でお召し頂ける実用的な着物です。正式には一つ紋を付けます。

小紋
本来は模様の大小を区別する呼称でしたが、現在では型染めや手描きなど染め柄の着物の総称として使われています。江戸小紋と友禅小紋に分類されます。 |
|
|
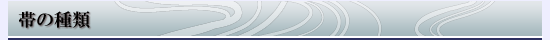 |
|
|
丸帯
女帯の一種。花嫁衣裳で使用されます。帯の種類の中で最も格の高い帯です。幅68センチの布を半分に折って仕立てられます。折りたたむ形状のため厚みと重量があり、現在では冠婚葬祭以外ではあまり用いられません。

袋帯
女帯の一種。
二枚の布を袋状に縫い合わせた帯。丸帯の代わりに礼装に用いられます。二枚合わせの表側が柄地で裏側は無地となります。軽くて仕立てやすい帯として、現在最も代表的な女帯といえます。

名古屋帯
女帯の一種。九寸名古屋帯とも言われています。大正七年不景気な時代背景から考え出された帯で、名古屋のデパートが売り出し全国に普及しました。現在では袋帯に次いで人気の高い帯といえます。

綴帯(つづれおび)
緯糸(ヌキイト=横糸)で模様を描きながら織り上げられた帯です。綴織の職人は指先の爪にやすりをあてのこぎり刃のように整え、その爪先で緯糸を掻き寄せながら丹念に織り上げていきます。

角帯(かくおび)
男帯の一種。男性の礼装に用いられます。厚みがあり堅い帯です。

兵児帯(へこおび)
和装用帯の一種。男性と男児、女児の普段着用の帯です。胴回りを二周させ後ろで結ぶ簡単な帯です。 |
|
|
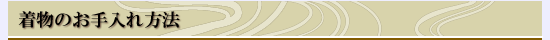 |
|
|
着物のお手入れ
一日着用した着物はシワが付いていますので、すぐにたたまず風に当てておきます。
自然に取れないと思われるシワは、弱めのアイロンを裏側から当てましょう。万一汚れがある場合は、着物専門のクリーニングに出すようにします。たたんだ着物は、たとう紙に包んでから箪笥へ入れてください。

帯のお手入れ
帯も結びジワが付いていますので、すぐにたたまず長く伸ばした状態でハンガー等にかけて風に当てておきます。深いシワはあて布をして弱いアイロンを当てて下さい。たたんだ帯は、着物同様にたとう紙に包んでから箪笥へ入れてください。

土用干し
梅雨の時期は着物や帯が湿気を含んでしまいます。この湿気をとるために7月下旬から8月上旬の間に着物の虫干しを行なう事を「土用干し」と言います。

寒干し
真冬の最も湿度の低時期(1月下旬〜2月下旬)に虫干しすることを「寒干し」と言います。主には、上等の着物が吸収してしまった湿気をとるために行ないます。 |
|
|
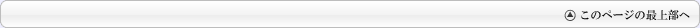 |
|
